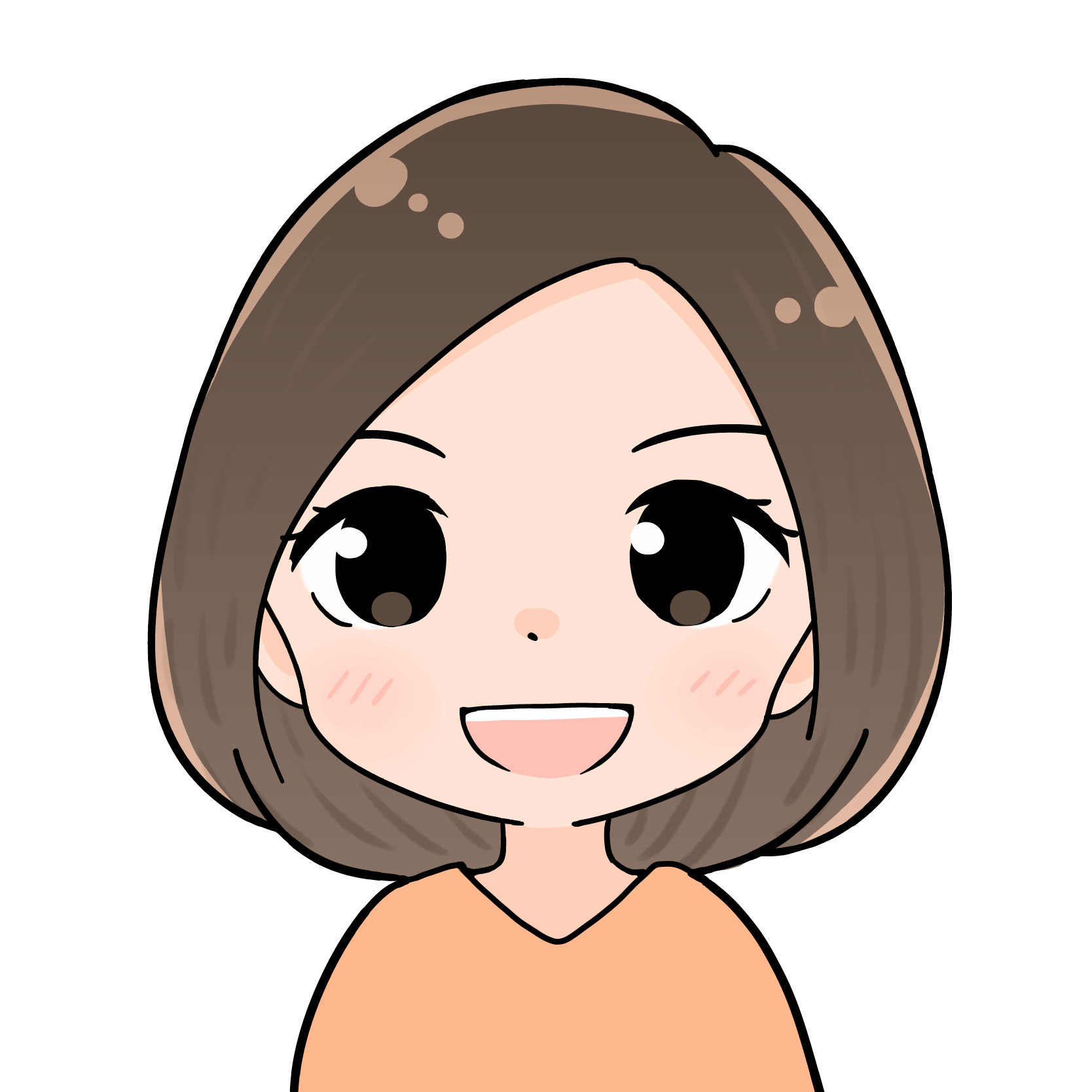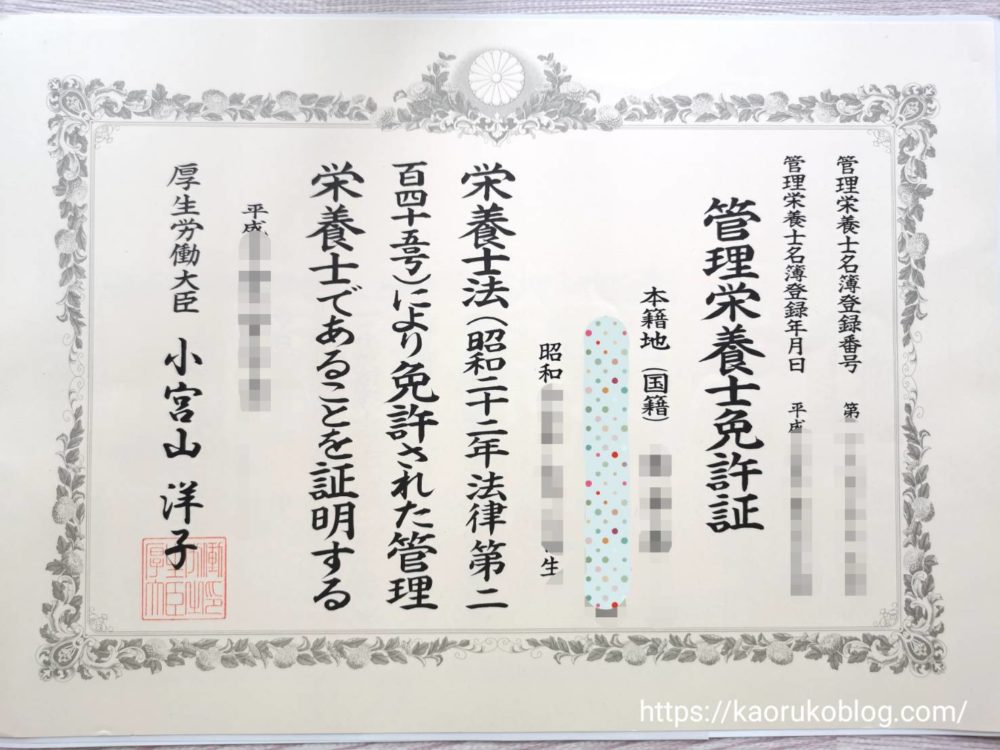
初めて離乳食をはじめるママやパパは離乳食と言われてもピンとこないと思います。
この記事では
- 離乳食ってなに?
- おさえておきたい離乳食の基本ルール
について解説します。
離乳食1日目の進め方については別記事で解説していますのでこちらもどうぞ。
離乳食ってな〜に?
 そもそも、普通に生活していて離乳食を見る機会ってなかなかないので離乳食自体のイメージがつかない方もいると思います。
そもそも、普通に生活していて離乳食を見る機会ってなかなかないので離乳食自体のイメージがつかない方もいると思います。
「2人目、3人目のお子さんの離乳食だから、離乳食のことはだいたいわかってるよ!」「とにかく食べられるようになればいいんでしょ!」って方は読み飛ばしてOKです。
- 離乳食は「飲む」から「食べる」へ進化するための練習
- 1才〜1才半ころまでに初期→中期→後期→完了期って進むよ
- 離乳食の進み方は赤ちゃんそれぞれだから周りは気にしなくていいよ
離乳食は「飲む」から「食べる」へ進化するための練習
 離乳食はおっぱいやミルクを飲んでいた赤ちゃんが噛んで食べる食事をするための練習期間です。
離乳食はおっぱいやミルクを飲んでいた赤ちゃんが噛んで食べる食事をするための練習期間です。
1才〜1才半ころまでに初期→中期→後期→完了期って進むよ
離乳食は5〜6ヶ月頃からはじめます。練習するために、最初はミルクみたいな液体に近いものから。
そして飲み込めるようになってきたら水分を減らしていって、1才〜1才半くらいになるときには大きめの食材をパクっと食べられるようになります。
離乳食の進み方は赤ちゃんそれぞれだから周りは気にしなくていいよ
 離乳食は初期〜完了期までで目安の月齢が決まっていますが、あくまでも目安です。体重もからだの発達もバラバラなのに、離乳食の進み具合が同じはずはないんですよね。
離乳食は初期〜完了期までで目安の月齢が決まっていますが、あくまでも目安です。体重もからだの発達もバラバラなのに、離乳食の進み具合が同じはずはないんですよね。
だから、「周りの赤ちゃんが離乳食進んでる」とか、「離乳食の本通りにいかない」とか気にしなくていいんです!
詳しくはこちらに書いています。

離乳食の基本ルール


①赤ちゃん自身の発達に合わせて離乳食を進める
離乳食本やこの記事に書いてある月齢はあくまで目安。赤ちゃんの体重や歯の生えかたも違うので、離乳食の進み具合は赤ちゃんそれぞれです。
トロトロ状から始め、歯の生えかたや口の動きの発達をみながら少しずつかたさを増していきます。
【関連記事】離乳食時期の赤ちゃんのお口の発達を解説



②食べ物は加熱する


【関連記事】食材を加熱するのはいつまで?



③味つけなしからはじめて、いろいろな食材を少しずつ増やす


離乳食を調味料で味つけするのは後期(9〜11ヶ月ころ)から。完了期(1才〜1才6ヶ月ころ)には使える調味料の種類が増えますが、1才を過ぎても大人の食事を2〜3倍に薄めるのが良いですね。
同時にいろんな食材を少しずつ増やしていき、大人の食事に近づけていきます。
【関連記事】離乳食の味つけはいつから?



【関連記事】赤ちゃんの味覚の発達について
④離乳食のNG食材を知る
- はちみつ
- もち
- かまぼこ
- そば
- 刺身・生卵
「はちみつ」は赤ちゃんが処理できない菌(ボツリヌス菌)を含んでいるため、1才までNG。また、のどに詰まらせる危険のある「もち」、塩分が多くかみにくい「かまぼこ」もNG。「そば」はアレルギーの心配があります。「刺身、生卵」などの生食もダメです。
⑤アレルギーに注意する


特に、3大アレルギーと言われる「卵」「小麦」「乳」をはじめてあげる時には注意してください。
【関連記事】離乳食の卵はいつから?



⑤スプーンの使い方を知る(スプーンを水平に引き抜くのがポイント)


- 下くちびるにスプーンをトントン
- 赤ちゃんがくちびるではさんで、上くちびるでとり込むのを待つ
- スプーンを水平に引き抜く
スプーンで下くちびるに軽くふれて、赤ちゃんに「食べるよ〜」というサインを送ります。赤ちゃんが口をあけたら、スプーンを下くちびるにおくだけ。赤ちゃんが自分の上くちびるで離乳食をとり込むのを待ちます。そのあと、スプーンは水平に引き抜きます。
- 上くちびるに沿って引き抜く
- 口の奥にスプーンを入れる
上くちびるに沿って引き抜くと、赤ちゃんが自分で離乳食をとり込む力が育ちにくいので、スプーンを引き抜く際は水平に引く抜くことを意識します。また、口の奥までスプーンを入れると、丸のみのくせがつきやすいです。
まとめ:離乳食の基本ルールを知っておくと安心
離乳食の進み具合は個人差が大きいです。
離乳食本通りにも進まないです。
ほんに書いてあることと違うと心配になりますが、この記事に書いてある基本ルールを守っていればあとは個人個人に合わせて大丈夫かなと思っています。
離乳食1日目の進め方については別記事で解説していますのでこちらもどうぞ。